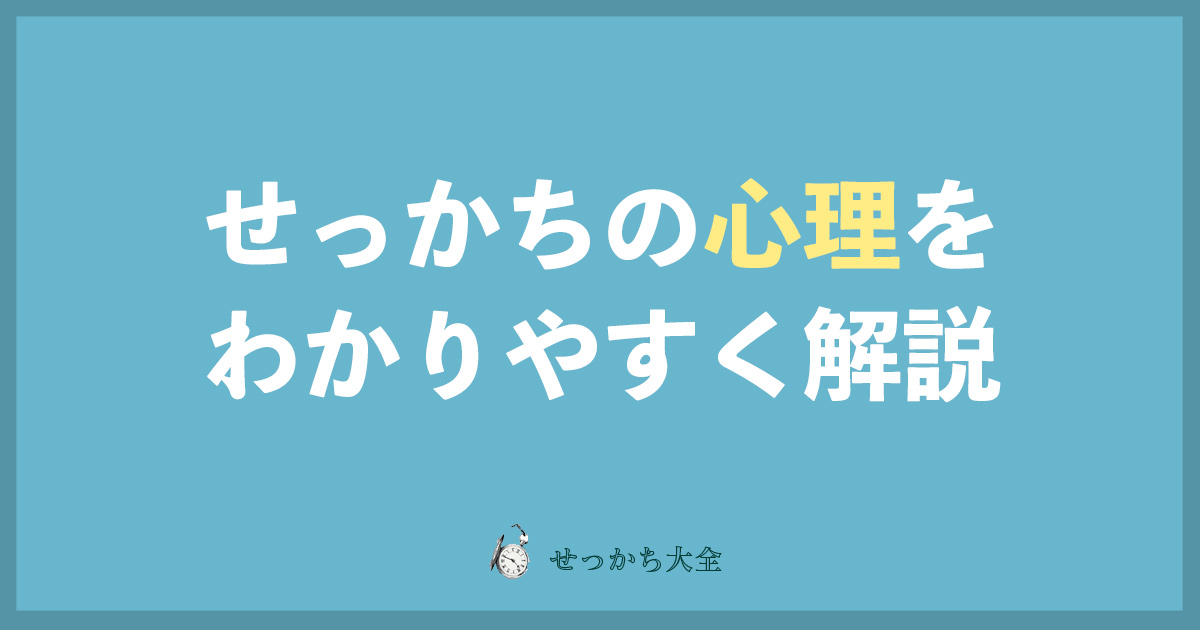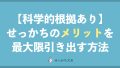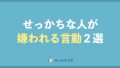「待たされるとイライラする」「すぐ結果を知りたくなる」「のんびりしている人を見ると急かしたくなる」──そんなせっかちな人が皆さんの周りにもいるかもしれません。
そんな人の心理はいったいどうなってるんだ?と疑問に思う方も多いと思います。
このページでは、心理学や神経科学の研究をもとに、せっかちの心理をわかりやすく解説していきます。
せっかちの基本的な心理は「早く決着をつけたい気持ち」
実は、人は誰でも、先のことがわからない状態におかれると、不安を感じたりイライラしたりする性質を持っています。
そのため、誰もが基本的には「早く結果を知りたい」「早くケリをつけたい」というような心理を大なり小なり持っているのです。
例えば、何かの試験結果を待っていることを考えてください。
結果を早く知りたいと思う気持ちは、その激しさは違えど、(何か個人的に結果を知りたくない特殊は事情がなければ)誰でも同じでしょう。
せっかちな人は、その度合いが強いわけです。
つまり、せっかちな人は、通常人間がみんな持っている「早く決着をつけたい気持ち」が強いというだけで、そういう気質はみんな持っているということです。その度合いには個人差があって、それがある程度のレベルを超えると周りからせっかち認定されるような感じですね。
2024年にアメリカ・シカゴ大学で行われた研究では、1871人の大学生や社会人を対象に実験を行い、以下の結論に達しました。
“Across seven studies (N = 1,871), we consistently find that people preferred to pay more money sooner over less money later when they had a stronger desire for goal closure. This pattern emerged across different contexts and payment types, suggesting a robust effect of closure motivation on intertemporal choices. Rather than reflecting a myopic desire for the reward, preferences for sooner options may instead reflect a desire to finish the transaction or, more broadly, to achieve goal closure. These findings highlight that impatience in economic decisions can be driven not only by the valuation of rewards but also by the psychological need to bring closure to an ongoing goal.”
(7つの実験(参加者合計1,871人)において、人々は「より少ない金額を後で支払う」よりも「より多くのお金を早く支払う」選択を好む傾向を示した。このパターンは異なる文脈や支払い方法でも一貫して見られ、決着欲求(closure motivation)が時間選好に強い影響を与えていることを示している。これは単に報酬を早く得たいという近視眼的な欲求ではなく、「取引を終わらせたい/目標を完了させたい」という心理的欲求に基づく可能性がある。これらの発見は、経済的意思決定におけるせっかちさが、報酬の価値評価だけでなく、進行中の目標に決着をつけたいという心理的ニーズによっても動かされることを浮き彫りにしている。)出典:Can’t Wait to Pay: The Desire for Goal Closure Increases Impatience for Costs(Roberts, Imas, & Fishbach, 2024, Psychological Science)
これは、一般的には、せっかちとは、「早く報酬を得たい」という特徴と言われていましたが、報酬ではなく「費用を支払うこと」について調査を行うことで、「早く支払ってしまいたい」「早くケリをつけて終わらせたい」という感情がせっかちの起因になっていることを突き止めた研究です。
支払いまでの期間が短ければ高額の支払いを、長く待てれば金額が減って少額の支払いで良くなる、という状況で、せっかちな人ほど「高額でもいいから早く支払ってしまいたい」、と感じるそうです。笑
脳とせっかちの関係
次に、脳とせっかちの関係についてです。
人間の脳は「ご褒美」をもらえるとき、強く反応します。
特に「すぐにもらえるご褒美」は、脳の報酬系と呼ばれる「快楽や報酬に関わる部分(線条体)」を強く刺激します。
つまり、誰でもこの線条体などがある程度は活性化するのですが、せっかちな人はより活性化して「すぐご褒美が欲しい!」となり、衝動的に行動に出てしまうというわけです。
これは、2024年にオランダ・アムステルダム大学で行われた研究で証明されました。
この実験では、「今すぐ得られる報酬」と「後で得られる報酬」を提示し、脳や行動を測定することで以下のような結果が得られました。
“The anticipation of immediate rewards increases approach behaviour, reflecting a Pavlovian bias toward action when rewards are available without delay. Participants showed stronger approach responses when immediate rewards were presented compared to delayed ones, suggesting that impatience is rooted in automatic motivational processes of the brain.”
(即時報酬を期待すると接近行動が強まり、報酬が遅れなく得られるときには「行動せずにいられない」というパブロフ的なバイアスが働く。実験参加者は、遅延報酬よりも即時報酬を提示されたときにより強い反応を示した。これは、せっかちが脳の自動的な動機づけプロセスに根ざしていることを示唆している。)出典:Pavlovian impatience: The anticipation of immediate rewards increases approach behaviour(発表年 2024, Cognitive, Affective, & Behavioral Neuroscience)
この研究では、MRIで脳を計測し、「小さいがすぐもらえる報酬 vs 大きいが後でもらえる報酬」の選択課題を行わせたところ、「前頭前野―線条体」の回路を中心に測定したところ、この回路の結合が強い人ほど長く待つことができ、結合が弱い人ほど待つことができないという結論に達したということです。
これが、せっかちの生物学的な根拠です。
子どもはなぜせっかちなのか
先ほどの似た研究として、子供のせっかちに着目したアメリカ・ワシントン大学の研究から、もう一つせっかちの心理をご紹介します。
子供は大人に比べて「待つこと」が苦手で、バスや電車でも到着までじっと待つことができない子供は多いですが、これは性格だけでなく、脳の発達とも関係しています。
先ほども見ましたが、人の脳の「前頭前野(冷静に判断する部分)」と「線条体(ごほうびを欲しがる部分)」の回路がその人のせっかち度を決定づけていましたが、この回路が、思春期にかけてつながりが強くなっていきます。
つまり、年齢が上がるにつれて「衝動をコントロールして待つ力」が少しずつ育っていくので、小学生や、もっと幼い子供たちは、この部分の結合性が弱いわことからせっかちな傾向が強いというわけです。
“Impatience decreases with age as frontostriatal connectivity strengthens, supporting greater self-control over time.”
(せっかちは年齢とともに減少し、前頭前野と線条体のつながりが強まることで、自己コントロールがより可能になる)出典:Adolescent impatience decreases with increased frontostriatal connectivity(van den Bos, Rodriguez, Schweitzer, & McClure, 2015, Proceedings of the National Academy of Sciences)
これも「たしかに」と思える研究結果ですね。
ゴールが近いほど焦る心理
ゴールが目前であったり、締め切りが迫ったりすると、イライラが強まった焦ったりすることがあります。
心理学の研究によると、人は「待ち時間の終わりが近い」「終わりが見えてきた」と感じるほど、焦りが強まり、せっかちになる傾向があります。
“Across six studies, we document that impatience accelerates as people approach the anticipated end of a wait. This pattern emerged in contexts ranging from waiting for a bus to arrive, to waiting for packages to be delivered, to waiting for the results of the 2020 U.S. presidential election and the distribution of COVID-19 vaccines. Importantly, impatience did not simply grow with the passage of time but increased disproportionately near the expected end. These findings suggest that impatience is shaped not only by elapsed time but also by people’s psychological sensitivity to anticipated closure.”
(6つの研究を通じて、待ちの終わりに近づくにつれて人々のせっかちさが加速することを明らかにした。このパターンは、バスの到着を待つ状況から、荷物の配達を待つ状況、さらには2020年米大統領選の結果発表やCOVID-19ワクチンの配布を待つ状況にまで共通して見られた。重要なのは、せっかちさが単に時間の経過とともに増したのではなく、終わりが近づくと不釣り合いに強まったという点である。これらの発見は、せっかちさが経過時間だけでなく、「決着(closure)」を予期する心理的感受性によっても形成されることを示唆している。)出典:Impatience Over Time(Annabelle R. Roberts, Ayelet Fishbach)
要するに、早く支払いを済ませたいとか、早く報酬が欲しいとか、そういったせっかちが発動するポイントが、時間的に迫ってくればくるほどさらにせっかちが加速する、というイメージですね。
終わりが近づくと安心するのではなく、むしろ焦るというのはちょっと意外なような気もしますが。
まとめ
せっかちは、以上のような心理や生物学的な根拠があって起こっています。
これらの研究は、心理学や神経科学、行動経済学によるものですが、それらをこのように冷静に客観的事実として眺めるだけで、せっかちの見え方が変わってこないでしょうか?
もしせっかちな気持ちが沸き起こった時は、上記のような心理的な反応が起こっているのだと思って、自分のせっかちを見つめてみると、せっかちが収まるきっかけになるかもしれません。
皆さんのお役に立てば幸いです。